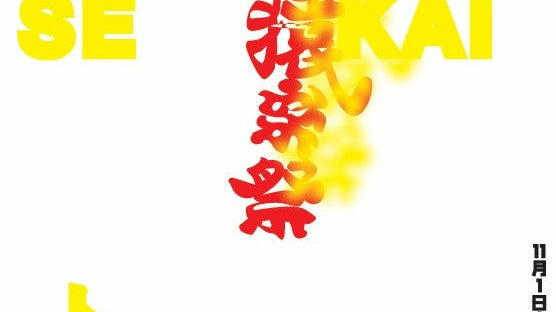日本人が昔から使い続けてきた「土」からできた器。
中でも、多くの陶芸家から評価されてきたのが信楽の土です。
熟練の陶工が丁寧に焼き上げることで、
その土は血色の良い人肌のような表情をみせ、
明るく温もりのある陶器が生まれます。
『TOU 』はこの信楽の土にこだわり、
プロの使い手目線から開発された業務用食器シリーズ。
飲食店の多種多様な要求に応えられるように改良を重ね、
料理を引き立たせる洗練された風合いと高い耐久性を実現しています。
勿論、一般家庭での日常的な利用にも向いており、
料理をつくる様々な人の創造性を高めます。





土から生まれた
業務用食器

信楽の伝統と革新が融合した、土の器『TOU BASIC』。
信楽の土の特徴を活かしつつ独自開発した強化粘土で「軽い・薄い・重なる・強い」を実現し、オリジナルデザインでプロダクト化された器です。
高度な窯業技術と熟練の手仕事でひとつひとつ丁寧に、深みのある味わいで温かみのある質感に仕上げてあります。
なめらかな釉薬で汚れが付きにくいため、ストレスなく洗えるのも魅力です。
軽くて扱いやすく、重ねてコンパクトに収納が可能で、電子レンジや食洗機にも対応しており、業務用としての耐久性も備えています。

信楽の伝統を受け継いだ熟練陶工の器『TOU Meister』。
それぞれの窯元が作り上げた個性豊かな器が、釉薬ごとにコレクションされております。
人工的な着色料を使用せず、天然の素材だけで作られた釉薬であること。高い窯業技術がいかされており、器に土の風合いがあること。無駄な装飾が少なく、飽きのこない器であること。飲食店での使用実績が豊富で、業務用としての耐久性があること。
これらの高い基準を満たした価値ある器を取り揃えました。
どの器も、一つ一つが出会いが感じられるよう丁寧に作られており、扱いやすく、使い込むほどに手に馴染みます。